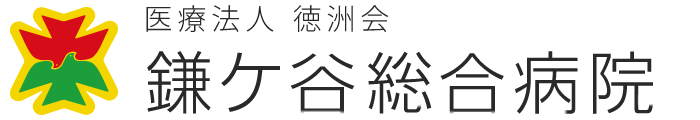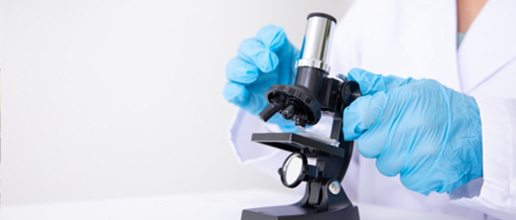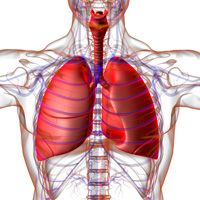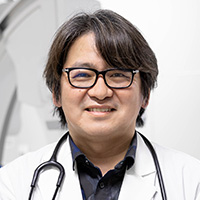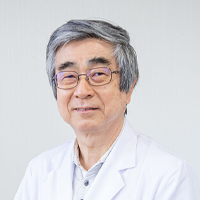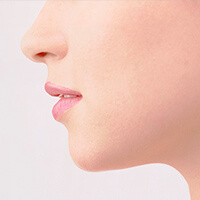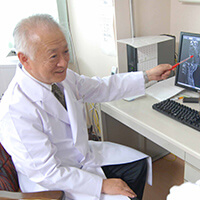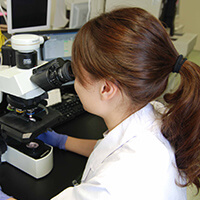5.慢性しゃっくりに関係深い基礎疾患
慢性しゃっくりに関係深い基礎疾患
基本的にしゃっくりは48時間以内に自然に止まるものだ、と考えられています。そう決まった経緯はよく分かりません。もしかすると「しゃっくりで一晩眠れなかったとしても、二晩は続かないもんだ、安心しなさい」という偉い先生のメッセージなのかもしれません。
48時間以上2ヶ月以内で続くしゃっくりを「持続性しゃっくり」と呼びます。さらに2ヶ月以上続くしゃっくりは「難治性しゃっくり」と呼ばれます。
しゃっくりが始まるきっかけで多いのが食事にまつわるもので、食べ過ぎや飲み過ぎもしばしばきっかけになります。そもそもしゃっくりが「飲み込み運動の一種」だと思っていますから、食事に関連するのは当然かもしれません。
しかし長期間しゃっくりに悩んでいる人は「ご飯とは全く関係ないよ」という事が珍しくありません。私が関わって来た方には68年間悩んでいた人を始め、平均病脳期間(=しゃっくりに悩んでいる期間)はなんと5.6年(中央値2年)です。要するに平均で5年半もしゃっくりが止まらないという人が世の中にはいらっしゃるのです。その様な難治性しゃっくりに悩んでいた方の基礎疾患を調査した結果、一定の傾向が分かってきました。
関連が深い疾患
- 逆流性食道炎(GERD、NERD)、機能性胃腸障害
- 糖尿病
- 脳出血、脳梗塞、頭部外傷
- 慢性腎不全、透析
- 脊椎骨折(胸椎)
- 胃手術後(特にビルトートII法再建後)
その他に、脳腫瘍(転移性脳腫瘍を含む)や食道癌術後、あるいは抗癌剤治療中といった方にもしつこいしゃっくりが起こることは知られています。
まだ他にもあるかもしれませんが、重要なのは「実は未知の病気が隠れている」というよりも、むしろ「はっきりしたしゃっくりの原因がある」方が遙かに多いということです。
[コラム] なぜしゃっくりは意識的に止められないのか? しゃっくりを発生させる震源地は「しゃっくり中枢」と呼ばれ、脳の中でも延髄という部位の中にあります。我々の意識は主に「大脳」にあります。大脳では自分で体に命令を出すことができます。例えば「右手を挙げよう」とか「深呼吸しよう」と思えば、思い通りに体を操ることができます。一方の延髄は体内の内臓その他、全ての臓器の働きを一括して管理しています。例えば体温、血圧、呼吸の速さ、心臓の動き、胃液の分泌などなど、生命維持に必要な活動を、延髄が一括管理してくれているお陰で、我々は苦労なく生きられる訳です。逆に言えば、延髄は「完全自立型」なので、我々が意識でコントロールすることは不可能です。「しゃっくり中枢」は延髄の中に存在するので、その活動を意識で止めることができないのです。