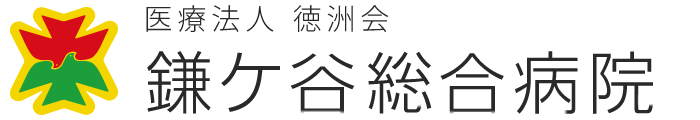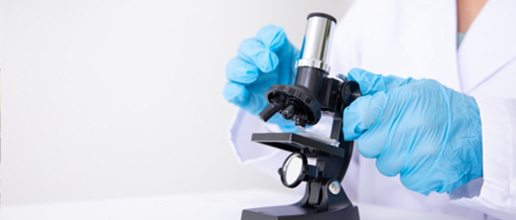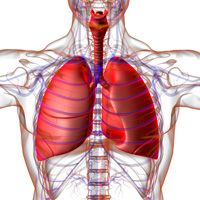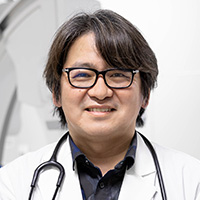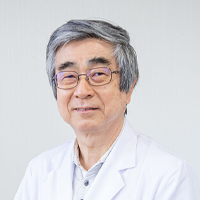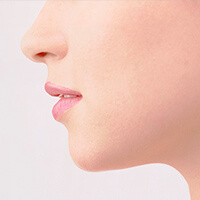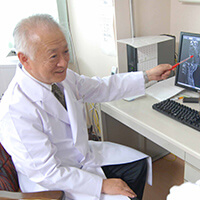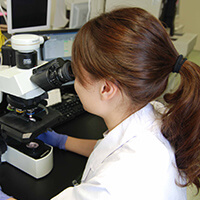2.新解釈:横隔膜の進化と役割
新解釈:横隔膜の進化と役割
巷では「しゃっくりは横隔膜のけいれん」と言われています。確かにしゃっくりで一番大きな動きをするのは横隔膜。だから横隔膜が根本原因だと考えるのも無理ないでしょう。ところが、実はしゃっくりは横隔膜だけで起きている現象ではありません。喉付近の筋肉(例えば声帯を動かす筋肉)も同時に動いています。その証拠に、しゃっくりをすると「ヒック!」という「声」が出ます。横隔膜と共に声帯を動かす筋肉が動くからです。つまりしゃっくりを「横隔膜のしわざ」とするのは、まさに木を見て森を見ず。大木だけに目を奪われて、周囲の小さな木々に気づいていない見解のように思います。
[コラム] 横隔膜 横隔膜を動かす神経は「横隔神経」。首の骨の間を通って(第4頚椎付近)首を通り、胸の中を通って横隔膜に到達する長い神経です。左右それぞれにあり、左右の横隔膜はそこから流れてくる電気信号で動いています。余談ですが、慢性的に続くしゃっくりを治療するために、左右両方の横隔神経を切断する手術(!)が日本でも行われたという記録があります。確かにこの手術を行えば、しゃっくりが起こっても横隔膜は動きません。しかし喉周囲に行く神経はしゃっくりが起こると動きます。つまりしゃっくりの度に声帯などが閉じる、すると息が一瞬止まるはず。 だから患者さんは真の意味では満足しないはずです。しかも横隔膜が動かなければ、普段の生活で深呼吸ができません。まさに本末転倒。海外では未だにこの手術が行われているようですが、私はこれに反対です。
さて横隔膜の役割は? といえば、多くの人が「呼吸」と答えると思います。もちろん教科書的には大正解ですが、あえて私は「半分正解」と致しましょう(理由は後述)。
では動物はすべて横隔膜で呼吸しているのでしょうか? いいえ、違います。実は横隔膜を使って呼吸している生き物はむしろ少数派。例えば鳥には横隔膜がありません。しかし鳥は人間よりも遙かに酸素摂取能力が高い、効率的な呼吸システムを持っています。何しろ鳥は空気の薄いはるか上空でも酸素を摂取でき、空を自由に飛んでいます。中にはヒマラヤ山脈上空を飛べる鳥もいます。単純に酸素摂取効率を追求するなら、「鳥方式の呼吸システム」を持てばよかったはず。なのになぜ我々の祖先は、わざわざ効率を犠牲にした「横隔膜方式」を選んだのでしょうか? 私は、先祖の選択は大英断だったと思うのですが、その英断に横隔膜の「真の役割」が隠れています。
[コラム] 鳥の肺は一方通行式、ヒトの肺は往復式 鳥の肺は、吸い込んだ「新鮮な空気」だけが肺を通過する「一方通行方式」です。肺を通過した「古い空気」は裏口を通って、二度と肺を通過することなく排気されます。鳥方式では新鮮な空気と古い空気が混じる事がないので、吸った空気は100%有効に酸素摂取に使われます。 一方、人間の肺は空気の出入り口が1つしかない往復方式。そのため吸った新鮮な空気と捨てたい古い空気は常に混じり合って存在しています。しかもせっかく入ってきた新鮮な空気でも、最後に入ったものは、肺にたどり着くこともないまま、すぐ逆方向に押し戻されます。これが出入り口の一カ所しかない横隔膜方式の欠点。肺にたどり着けないまま捨てられる空気の量は成人で約150cc。成人が普通に呼吸している時、1回に吸い込む空気の量は約500ccですから、なんと吸った空気の30%が酸素摂取に使われることなく無駄に捨てられています。 鳥方式と横隔膜方式。酸素摂取効率だけに注目すると、呼吸システムは鳥方式に軍配が上がるでしょう。
横隔膜を持つ動物とは? そうです、哺乳類です。ちなみに哺乳類は単孔類(カモノハシなど)、有袋類(カンガルーなど)、有胎盤類(イヌ、ネコ、ウシ、ヒト・・・など)を指しますが、共通するのは「母乳で赤ちゃんを育てる」ことです。
すると「横隔膜は、母乳を吸えるように発達した臓器ではないか?」という推論が成り立ちます。それを検証しましょう。
結論から述べると「横隔膜は、母乳(液体)を吸うために先祖が獲得した筋肉である」と私は考えます。古代生物を研究した日本人学者によると、横隔膜は元々肩付近にあった筋肉だったそうです。それが長い年月をかけて現在の位置まで下がってきたと結論づけています。ではなぜ哺乳類の先祖達は、肩にあった横隔膜をわざわざ現在の位置まで移動させてきたのでしょうか? おそらく先祖達は横隔膜に呼吸以外の仕事をさせたかったからだと思います。
簡単な実験をしてみましょう。コップに入れた水をストローで吸ってください。最初に息を全部吐いたところから水を吸ってみましょう。簡単に吸えると思います。次に大きく息を吸い込み、これ以上もう吸えないというところから水を吸ってみましょう。今度は水をほとんど吸えないはずです。
そうです、横隔膜は液体を吸い込む原動力だったのです。横隔膜で「陰圧(例えるなら掃除機のように吸い込む力)」を作り出すことで、哺乳類は効率よく液体を吸うことができます。つまり哺乳類が横隔膜を獲得したのは、赤ちゃんが母乳を吸うため。言い換えると、横隔膜が哺乳を可能にした=哺乳類だけが横隔膜を持っている理由だと思います。
自然界には周囲にたくさんの敵がいます。特に弱い赤ちゃんは格好のエサとなります。しかし哺乳類が横隔膜を獲得したことで、赤ちゃんは母乳を吸って育つので、常に母親から離れることなく成長できます。敵が来ても子供達をいつも母親の手元に置いて守ることができるのです。一方、鳥はどうでしょうか? 親鳥は巣を離れてエサを取りに行かなければなりません。その間に子鳥は危険にさらされ、ヘビや猛禽類に襲われることもしばしば。哺乳類の先祖が酸素摂取効率を犠牲にしてでも、横隔膜方式を採用したのは、母乳を吸わせ、子孫をより安全に育てる知恵だったのです。哺乳類の先祖、えらい!って思いませんか?
と言うわけで、横隔膜の役割とは何か? 「呼吸と哺乳(飲食/摂食)」でした。横隔膜が作る陰圧は、肺に入る空気だけでなく、胃に入る食物を吸い込むためにも日々使われています。
[コラム] 横隔膜はどこにある? 横隔膜はおよそ「みぞおち」の高さにあります。本来、みぞおち付近の筋肉は、胸の脊髄神経とつながっています。ところが横隔膜を動かす横隔神経は、首の脊髄神経とつながっています。おそらく遠い昔、先祖の横隔膜が肩付近の筋肉だったので、その名残で首の脊髄神経とつながっているのでしょう。
[コラム] ”飛ぶ”といっても・・・ コウモリは哺乳類ですが、鳥のように空を飛ぶことができます。空を飛ぶためには大量の酸素が必要ですから、横隔膜で呼吸しているコウモリは大変強力な呼吸能力の持ち主なのでしょう。しかし空を飛ぶことにかけては、優れた酸素摂取能力を誇る鳥の方が一枚上手。無警戒に飛んでたら、あっという間にコウモリは猛禽類のエサとなるでしょう。そこでコウモリは鳥が寝静まった夜にこっそり出かけていきます。そして夜でも飛べるように超音波エコーを身につけました。
[コラム] 圧力と重力 水が高いところから低いところに流れるように、物体は圧力の高いところから低いところに移動します。一番有名なのは高気圧と低気圧。圧力の高い高気圧から低気圧に向かって空気が移動するので風が吹きます。同じ理屈で哺乳類は横隔膜で体内に陰圧を作ります。その陰圧によって水が体内に吸い込まれるので、水を飲むことができるのです。では横隔膜のない鳥はどうやって水を飲むのでしょうか? 鳥は水を飲むとき上を向きます。すると重力で口の中の水は低い方に移動します。おそらく鳥は重力を使って水を飲んでいるのでしょう。
[コラム] 唾液の役割 私が子供の頃「唾液は消化液だ。よく消化するように一口食べたら100回噛みましょう」という健康法がありました。しかし実際に100回も噛むと食べ物は跡形もなく水のようになり、味もなくなりおいしくありません。しかも食事時間がやたら延びるので、この健康法はすぐに廃れました。その後、自分が大学生になっても唾液の概念に進化はなく、相変わらず「唾液は消化液」とされたままでした。 ところがその後、英国の有名な科学雑誌に「唾液の機能」について論文が発表されました。「唾液とは、かみ砕いた食べ物同士をゆるやかにくっつけ、『液体』として飲み込むための接着剤だ」という説でした。目からうろこ(!)でした。唾液は、消化液というよりも「かみ砕いた固形物を包んで液状化させる役割」がメインだったのですね。実際、医療の現場では、誤嚥(食事するとむせることを)しやすい人のために「とろみ」をつける専用のペーストが使われています。余談ですが、有名なミュージシャンが、嫌いな食べ物はビスケットだと言っていました。理由は「唾液を全部吸い取られるから」だそうですが・・・確かに乾いた口でビスケットを食べると、かみ砕いたビスケットの粉を吸い込んでむせそうですね。