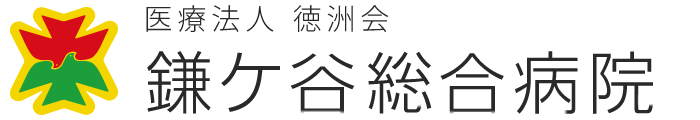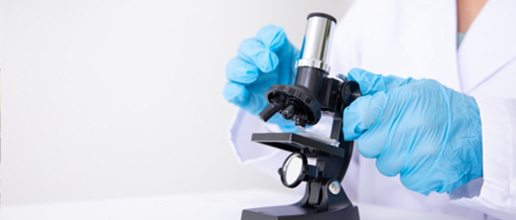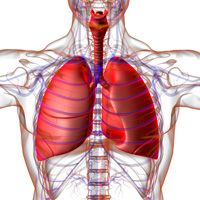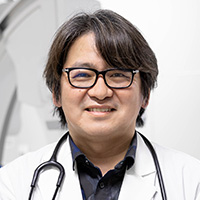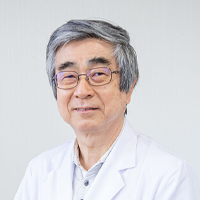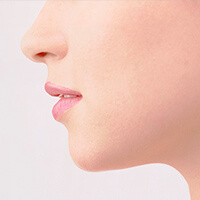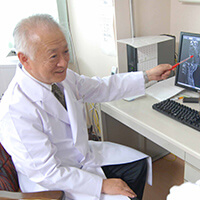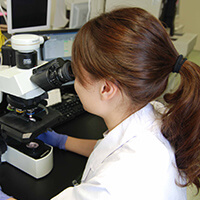6.現在出ているしゃっくりの止め方
現在出ているしゃっくりの止め方
古今東西、文献やネットに出ているしゃっくりの止め方は大きく5つに分類できます。
- 水を飲む系
- 息を止める系
- 別のことに意識を集中させる系
- 喉などに刺激を加える系
- 内服薬、注射薬
ちなみに日本に現存する最古の医学書「医心方」(=平安時代版「今日の治療」といった開業医向けの本にあたるのでしょうか)にはしゃっくりの止め方に関して記載があり、「冷たい井戸の水をたくさん飲む」とか「できるだけ長く息を止める」などの治療法が載っているそうです。上記の1)、2)に分類されますね。
それぞれの治療法について少し解説を加えておきます。
①水を飲む系
水を飲むことに意義は、脳に「食道の『異物』はすっかり胃に流されて、食道内はクリアになりました」という情報を送り、脳にしゃっくりはもう不要です、と認識させることです。
4章で述べた、しゃっくり発生のメカニズムを思い出してください。しゃっくりのきっかけは「食道に食べ物が詰まった」という情報が脳に伝えられることでした。実際、食道におにぎりが詰まった時は、皆さん、お茶かお水を急いで飲んで流し込もうとします。引っかかったおにぎりが胃に流れるとスッキリしますよね? まさにそれと同じ事をやっているわけです。
普通のしゃっくりの場合、食道には何も引っかかってはいません。しかし、ゴクコク飲んだ冷たい水が食道を流れていくと、脳は「食道には問題なく水が通過しているぞ」と認識するわけです。それにより脳にしゃっくりは不要ですよ、と知らせているもの、と解釈できます。
②息を止める系
息を止めると、人間にとって最も重要な酸素が入ってこなくなります。本当に酸素が減ると人間は意識を失い死んでしまうので、意識を失う前に「酸素が減っていること」を察知して命を守る何らかのメカニズムがあるはずです。
実は、人間の脳は「二酸化炭素濃度(以下、CO2濃度)」を常にモニターしています。それを指標に体内の酸素が減ってないかの指標にしているのです。動物はCO2濃度の変化にとても敏感です。なぜなら自然界でCO2濃度が上昇する場所は何かの動物が近くにいる場所だったり、あるいは狭く閉じ込められるような場所だったりと、本能的に緊張する場所だからだと考えられます。人間も例えば満員電車など、人いきれがする場所では暑苦しく感じますが、それもCO2濃度のわずかな上昇を察知して、体が反応している証拠なのです。
体内の炭酸ガス濃度は概ね4~5%(註:科学的には濃度ではなく、圧力で表現します。ここではわかりやすく濃度としました)。この濃度が0.1%増加しても、動物は敏感に反応します。体内に酸素が十分に残っていてもCO2が増加すると人間は不快に感じるのです。
呼吸を止めると、体内のCO2濃度は急速に上昇します。すると体内の酸素がまだ十分残っていても、人間は苦痛を感じ始め、呼吸を再開してしまいます。要するに体内のCO2濃度のモニターは、本当に酸素不足が起きる遙か前に「呼吸しなさい!」と人間に警告するためのものなのです。
詳しいメカニズムは横に置き、結論から言うと、体内のCO2濃度がおよそ7%まで上昇するとしゃっくりは止まります。つまりそれ以上のCO2上昇は「死んでしまう。しゃっくりなんかしてる場合じゃない!」と脳が「優先順位」を酸素の確保に全集中する、最終ラインなのです。
つまり息止めをする方法は、体内のCO2濃度に敏感だという人間の本能を逆手にとった優れた方法だと言えるでしょう。
③別のことに意識を集中させる系
人間は周囲の環境により色々な反応をします。例えば足下にヘビがいたことに気づいた時、大抵の人はびっくりしますが、その時、心臓が急にドキドキしたり、呼吸が速くなったり、冷や汗が出たり、と色々な身体的な反応が起こります。これらの反応は無意識に起こりますが、これこそまさに延髄などによる「自律神経の働き」です。血圧の上下や心臓の動き、体温調節等々、自律神経の働きは自分でコントロールすることはできません。
ところが自律神経にも優先順位があります。例えば、右にヘビ、左にヒグマがいることが分かったとします。ヘビも気持ち悪いですが、ヒグマに襲われたら命がありません。仮にヘビに噛みつかれようが、ヒグマから逃げることに必死になるでしょう。命を落とすくらいなら、ヘビに近づいてしまっても、全くこわくないかもしれませんね。
このように、脳は目の前にある2つの事態に対して優先順位を勝手に付けて、人間に対応を迫ります。そしてより緊急度が高いと判断した方に意識が集中するのです。
イギリスでは、しゃっくりを止める方法として、唐突に「君のお母さんのミドルネームは何?」って質問するやり方があるそうです。日本で例えるなら「君のお母さんの旧姓は?」という質問に近いかなと思います。確かに普段考えたこともないけど、記憶の隅には残っていそうなことを唐突に尋ねられると、記憶を掘り起こしてしばらく考え込みますよね? ところが面白いことに尋ねられた人のしゃっくりが止まるそうです。日本でも似た方法があるようで、ユニークなのは「ナスビの色は何色?」となぞなぞを出すというもの。古今東西、似たようなことを思いつく人がいるもんですね。
両者に共通するのは、「絶対に答えを知っているけど、答えを思い出すために少し集中して考える必要がある質問だ」ということです。一言で言うなら「意識を集中させる必要がある」ということでしょう。人間は「意識を集中させる課題」を与えられると、それに脳が没頭します。それによって脳は、しゃっくりさせる命令のことをすっかり忘れて、新しい課題に取り組むことで、しゃっくりを忘れてしまう、つまりしゃっくりが止まるのだと考えられます。
それの証拠?なのか、イギリスの母親のミドルネームを聞く質問は1回しか効かないそうです。一旦脳が答えを思い出すと、次からはすぐに答えられるので、意識を集中させる必要がなくなるのでしょうね。
以上のように、しゃっくりは脳から命令が出ていることを利用して、脳に「もっと急ぐ用件だ」と判断させるような仕事を与えることで、しゃっくりのことを忘れさせるのは、道理にかなっていると思います。
④喉などに刺激を加える系
指や細い管を喉の奥に突っ込み、嘔吐反射を起こさせると止まる人がいます。実際に嘔吐するとしゃっくりが止まるという人もいます。繰り返しますが、しゃっくりは「食道に詰まったものを胃に移動させる反射」です。食道に詰まったものが吐き出された、と脳が認識すると、確かに理論上はしゃっくりが不要になりますね。 おそらく脳がそのように判断することで、しゃっくりが止まるのでしょう。
⑤内服薬、注射薬
基本的に5系統の治療薬があります。
しゃっくりのメカニズムは「食道の刺激」が脳に伝わり「脳からしゃっくりの命令が出る」というものでした。従って「消化管に作用する薬」と「脳に作用する薬」に大きく大別されると思います。それとは別に「しゃっくりは横隔膜の痙攣である」という考え方から、筋肉の痙攣を止める薬も治療薬として挙げられています。それを分類すると以下の5種類くらいになると思います。
- 胃薬(制酸薬、抗潰瘍薬)
- 吐き気止め(制吐薬、腸管蠕動促進薬)
- 炎症止め(抗炎症薬、鎮痛薬)
- てんかんの薬(抗てんかん薬、向精神薬)
- 漢方薬
これについては「一家言ある」という先生方の解説をご参照ください。それぞれ有効性は学術的な論文や報告が数多くあります。個人的には有効性の期待できるものと、それほどでもないものはあります。ここではその見解を控えさせて頂きますが、ちなみに筆者は①と③の組みあわせ、もしくは③で治療しています。
⑥ツボ刺激(鍼灸・指圧)
針治療や指圧が有効とされ、実際ネットには情報があふれています。論文もありますが、ほとんどが中国からの報告です。そのため信憑性について疑問を呈する西欧の医師は少なくありません。それに対する中国人医師の反論も載っていますが、西欧の医師は鍼灸を行わないので確認できません。筆者も針治療の知識や経験がないので、その有効性については論文を参照して下さい。